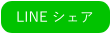特集・コラム

清水寺周辺の映えスポット
清水寺は京都の中でも特に人気の観光エリアになっております。古き良き京都らしい街並みが広がっているので着物散策にぴったりです。
本日は、こちら清水寺エリア~三年坂・二年坂~円山公園までを一緒に街歩き目線でご紹介致します!
★清水寺
まずは、定番中の定番・清水寺からご紹介をスタートします。清水寺は何と朝6時から開門されている為、時間がない方にもお勧めできます。坂を上がってくると、遠くから見えるのは朱色の三重の塔。高さは31mです。清水寺の拝観券のイラストにもなっている有名な塔です。実は清水店の拝観券、春夏秋冬、季節ごとにデザインがある事を知っていますか?拝観券と三重の塔を、その季節ごとに一緒に撮るのがなかなか映えます。

清水道より清水寺に到着すると、こちら眼前に朱色の仁王門がそびえ立ちます。境内では、季節に応じて春は梅・桜、夏は新緑、秋は雲海のような紅葉とそれぞれにまた違った世界を見せてくれます。






特にオススメなのが、雪が降り積もった日の清水寺です。京都に住んでいても、一年に1.2度見られるかどうか。真っ白な雪の中に写る朱の建物はとても幻想的に見えます。こんな日に京都に訪れる事が出来た人はとっても運がよいと思います!


さて、中へ進むと「清水の舞台」として有名な本堂が現れます。「清水の舞台から飛び降りる」という慣用句がありますが、その昔、実際願掛けとして飛び降りていたそうです。そう思って下を覗くと、ドキドキしますね。清水の舞台と一緒に写真を撮るなら、さらに奥に進んで奥の院より撮るのがお勧めです。ちなみに清水の舞台は、「懸造り(かけづくり)」と呼ばれる釘を使わない特殊な建築構造で支えられているので、観察してみてはいかがでしょうか?!

清水寺にはまだまだ映えスポットが沢山あり、奥の院を下ると音羽の滝が出てきます!祠(ほこら)から伸びる水流は三本に分かれており、それぞれ違ったご利益になっています。柄杓で掬い飲み干すことで願いが叶うとされていますので、一つだけ選んで飲んでみましょう(欲深いと願いが叶わなくなります)ご利益は、右から「健康」、真ん中は「美容」、左端は「出世」だそうです。実は、清水寺は、「北へ清泉を求めて行け」と夢のお告げを受けた僧が、この滝を見つけたことが始まりです。その後、僧の教えに感銘を受けた坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)により778年に清水寺が開創されたそうです。

また、清水寺では年に3回の青龍会が開催されます。長さ18メートルの観音様の化身である龍が、境内と門前町を練り歩きます。是非ご覧になってはいかがでしょうか?
• 青龍会 毎年3月15日、4月3日、10月15日
14:00ごろから1時間弱程度
経路:奥の院→音羽の瀧→西門→門前町→仁王門→本堂



★三年坂・二年坂エリア
三年坂の名称の由来を知っていますか?大同3年(西暦808年)に開けたからだそうです。初めて聞く年号です!三年坂を上った清水寺の塔頭に、安産祈願の子安の塔があることから、産寧坂とも呼ばれています。

坂を下るとすぐに瓢箪が沢山ぶらさげられたお店が出てきます。突如現れる瓢箪屋さんを不思議に思っていたのですが、実は三年坂は転ぶと「三年以内に死ぬか、三年寿命が縮む」という言い伝えがあり、瓢箪を持っていると、魂を瓢箪が吸い戻してくれるということで、瓢箪屋さんがあったのですね。因みに、三年坂の下の坂は二年坂と言います。

★法観寺(八坂の塔)
三年坂をおりて道なりに進むと法観寺・八坂の塔が見えてきます!高さは46メートル!真下から見上げても圧巻です。なんとあの聖徳太子が夢のお告げを受けて作ったのだとか…。夢のお告げで建てられるお寺が多いですね!何度も焼失しているので、現在の塔は1440(永享12)年に足利義教によって再建されました物になります。実は内部拝観が可能で、五重塔の2階まで見学可能です(但し、公開については不定休です)一階には、御本尊の五智如来坐像があります。八坂の塔には、西暦952年に、八坂の塔が傾いた際に、平安時代の有名な僧侶の祈祷で、一日で傾きが元通りになったという民間伝承があります。

★八坂庚申堂
上記の僧侶が八坂庚申堂を建てました。こちらは、SNSで、一度は目にしたことがある方が多いのではないでしょうか?インスタ映えスポットして有名な場所ですが、まず本堂にお詣りをしてから写真撮影をしましょう。

最初にカラフルなお堂が目に入ります。お堂の中に居るのは…?お釈迦様の弟子である十六羅漢の筆頭である「びんずる尊者」です。こちらのお堂を埋め尽くしているのは、色とりどりの「くくり猿」。見た目はまるでお手玉。何故くくり猿と呼ばれるかというと、お猿さんが手足をくくられて、動けない姿を現しているという事でした。動き回って落ち着かない人の心を猿に見立てくくることで、庚申さんに心の乱れをコントロールして頂き、願いを叶える…!という事だそうです。参拝客の皆様も、願いを書いて、お堂に吊り下げてみてはいかがでしょうか?また、びんずる尊者は、病気を治す力があり、撫で仏とも呼ばれています。

さて、庚申堂の名前は有名ですが、庚申信仰とは何か知っていますか?こちらは中国・道教の三尸説(さんしせつ)と日本の信仰が絡み合って出来たものになります。
人間の体内に三匹の虫が住んでいるとされ、60日に一度、帝釈天の縁日(庚申日)に、人の就寝中に身体の中から抜け出して天に昇り、その人の犯した罪を帝釈天に報告するそうです。それに応じてなんと…寿命が縮められてしまいます!抜け出させない為には…眠らなければよい!という事で、庚申日は徹夜をします。八坂庚申堂も、庚申日には夜まで祈祷をしており、名物?!こんにゃく焚きもしています。次回は、4月21日です!
因みにこの三匹の虫ですが、にょろにょろした虫かと思いきや、頭に住む道士の姿をした虫、お腹に住む獣の姿をした虫、そして足に住む顔が牛で体が足(もはや妖怪?!)の虫だそうです。庚申堂の本尊は、この三尸の虫を抑える力を持った金剛童子・青面金剛(しょうめんこんごう)です。全身は青く、憤怒の表情をしている…とされていますが、実物を見た事がありません。こちらのご本尊は、なんと60年に一度のご開帳です。次回は、2040年との事。15年…は長いですね!また、見ざる、聞かざる、言わざるの3猿を従者としています。境内は至る所にお猿さんがおります。本堂の他、入口の門で上を見上げてみると、そちらにもお猿さんが…。知らずに、何度も素通りをしていました。カラフルなくくり猿の前で、お猿のポーズはいかがでしょうか?


また、境内では、梅の花(2025年度は、3月中旬が満開でした)や、遅咲きの桜(4月中旬頃予定)が楽しめます。

★円山公園
この地はその昔(平安時代)真葛やススキが生い茂る原野でした。鎌倉時代に、和歌の名所となり、時代により様々な変遷を経て、現在は京都随一の桜の名所になっております。春には有名な祇園枝垂れ桜を筆頭に、園内に桜が咲き乱れ、ライトアップも行われます。見頃の頃には沢山の屋台や、花見茶屋も出ます。桜の下で飲むお酒、優美ですね。
【日程】2025年3下旬~4月上旬(予定) 18:00~22:00
こちらで和傘やお面を使った撮影はいかがでしょうか?また、夏には、ひょうたん池の前にある柳の木の下で撮影すると、日本的なお写真が撮れそうです。

清水エリアの四季を通じた魅力…。少しは伝わりましたか?!
是非お着物姿でこちらのスポットを楽しんで頂ければ幸いです!
京都ならではの思い出づくりに、レンタル着物岡本で着物をお召しになり散策してみてはいかがでしょうか?
【この記事の著者】
レンタル着物岡本 清水寺店
〒605-0862 京都市東山区清水2丁目237-1-1
TEL: 075-525-7115
HP: www.okamoto-kimono.com
Instagram: rentalkimonookamoto
Tiktok: @rentalkimonookamoto